こんにちは、まるこです。
病院に勤めて10年が経ちますが、管理栄養士としてまだまだ未熟だと日々痛感しております。
私だけかもしれませんが、目の前の仕事に夢中になっていると、本来の病棟やNSTでの役割、栄養療法へのアプローチの仕方など、根本的な部分を忘れてしまうことがあります。
今回は、栄養管理の原点に立ち返る目的で、管理栄養士の業務内容についてまとめました。
 まるこ
まるこ方向性や日々の業務で迷ったら、いつでも振り替えられるように記録しておきます。
管理栄養士の役割
病棟常駐の栄養士
栄養状態の低下はもちろんのこと、栄養障害のリスクとして、血糖管理や減量、水分管理など栄養にかかわる問題がある患者がいれば、以下の内容を多職種と協議しながら介入する
- 食種や食事内容の見直し
- 食事量の調整
- 栄養指導の必要性の有無
ICU常駐の栄養士
- 水分設定量を医師と相談
- 経腸栄養プランの作成→医師に提示
- 糖尿病など既往歴の確認→持参薬確認
- 看護師に血糖チェック、内服薬開始を確認
- 栄養開始後の血糖の確認
医師から求められること(相談をうける内容)
- どのような食事オーダーが適切か
- 食事はどのくらい摂取できれば良いのか
- 食事ができない、または足りないとき、経腸栄養・静脈栄養のメニューはどのように組むのか
- 経腸栄養剤・流動食はどのように選択し、どのように使用するのか
NST活動
NSTスタッフに求められるもの
職種に関わらず、NSTスタッフに求められるものは栄養療法に携わるものとして必要な基本的知識・技術。
これを基本として、+各職種の専門性を生かした栄養療法へのアプローチが必要。
管理栄養士としての栄養療法へのアプローチ
専門性を生かした栄養療法へのアプローチ方法。
東口髙志先生が書かれた「NST実践マニュアル」には、管理栄養士のアプローチ方法は主に以下の12項目を挙げています。
引用:東口髙志著「NST実践マニュアル」
- 栄養アセスメントの指導・詳細な解析
- 経腸・経口栄養の衛生管理と管理法の指導
- 経腸栄養剤の詳細な選択・推奨
- 経静脈栄養例の経腸・経口栄養への移行推進
- 経腸・経口栄養法の詳細なプランニング
- 栄養障害例の抽出・早期対応
- 栄養療法に関する問題点・リスクの抽出
- 在宅栄養・院外施設での栄養管理法の指導
- 嚥下障害患者への対応
- 喫食・摂食状態の把握と評価
- 病院食(food service)の重視
- 生活習慣病(予防医学)への対応
経腸栄養
施設ごとに使用している栄養剤についての知識はもちろんのこと、経腸栄養開始または移行する際に、対象患者の必要栄養量を把握したうえで、
- 何の種類の栄養剤を
- どのくらいの量から開始して
- いつまでにどのように増やして
- 最終ゴールはどこに設定するか
といった経腸栄養プランを提案できると良いですね。
また、病院食の内容や栄養補助食品の詳しい成分・効果を誰よりも詳しく把握し、病態に合わせて提案できる力も必要。
チームの中で、管理栄養士にしかできないこと!!!!
他職種が管理栄養士に求めることって主に以下のことなのではないかと思います。
1 患者の必要量(水分・栄養)を計算する
体重、検査値を見て、病態に合わせてあんなに細かく計算しているのは栄養士くらい?
2 各栄養投与ルートから、どれくらいの栄養が投与・摂取できているか計算する
食べられなくて、ENやPNを併用している方って、多くの場合、食事が細かく調整されていますよね。ハーフ食だったり、栄養補助食品がついていたり、持ち込み食を食べていたり…。摂取量や投与量からどのくらいの栄養が摂れているか、栄養士くらいしか知らないはず…!
3 では、①と②を踏まえて、どのくらい不足しているか把握する
4 どの投与ルートを使って、必要量を充足させるか考える
引用・参考資料
藤田医科大学第一教育病院(愛知県豊明市)栄養サポートチーム(NST) – がんプラス (qlife.jp)
新近森栄養ケアマニュアル
レジデントのための食事・栄養療法ガイド



今後追記する予定です。
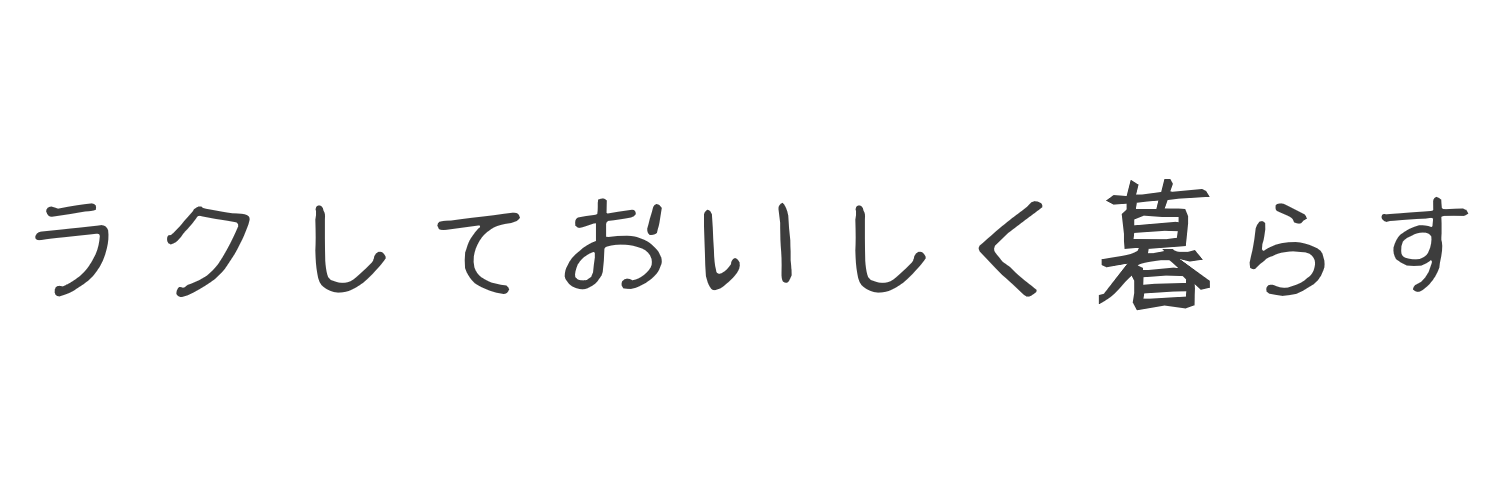
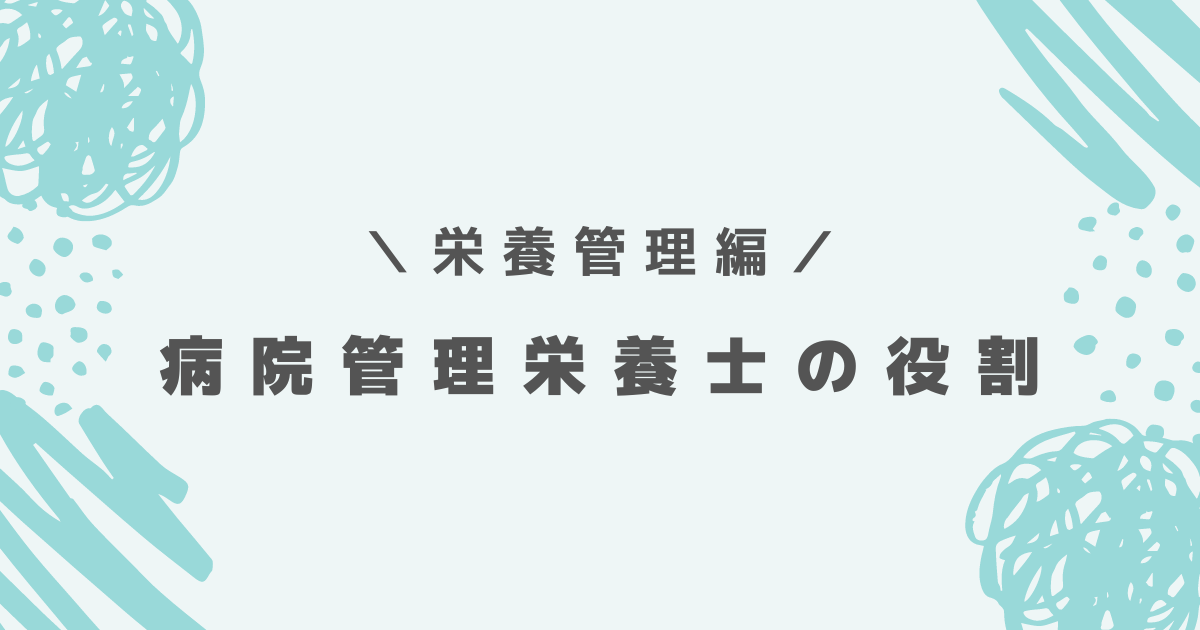


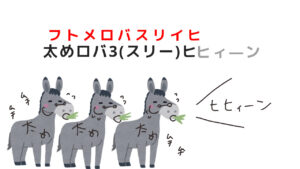

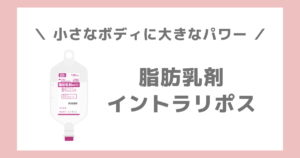

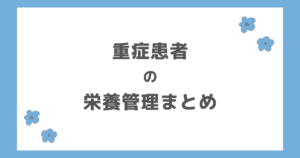
コメント